- 2025年8月9日
生活習慣病・メタボリックシンドローム
健康な未来のために知っておくべきこと

「生活習慣病」という言葉はよく聞くけれど、具体的にどんな病気を指すのか、ピンとこない人もいるかもしれません。しかし、生活習慣病は、日々の食習慣や運動習慣などが深く関わるため、私たちの心がけ次第でそのリスクを大きく下げることができる病気です。
そして、その中でも特に注目すべきが「メタボリックシンドローム」。これは、さまざまな生活習慣病の入り口とも言える状態です。この記事では、生活習慣病の定義や種類、原因、そしてメタボリックシンドロームとの関係性、さらに健康な未来のために私たちができる備えについてご紹介します。
生活習慣病とは? なぜ今、注目されるのか
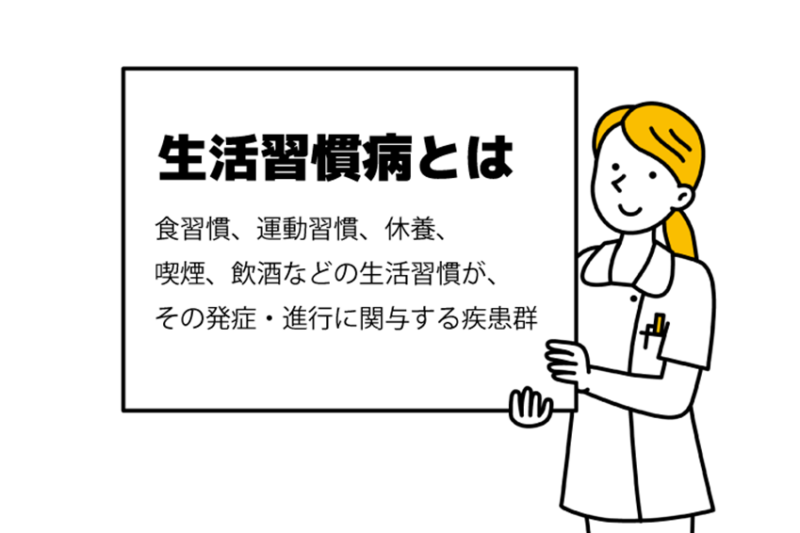
厚生労働省の資料によると、生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」 と定義されています。
以前は「成人病」と呼ばれ、加齢とともに発症・進行すると考えられていました。しかし、実際には、運動不足や飲酒、喫煙、不規則な生活など、子どもの頃からの生活習慣が原因となって発症することが明らかになり、近年では「生活習慣病」と呼ばれるようになりました。これは、年齢に関わらず、誰もが健康的な生活習慣を心がけることの重要性を示しています。
なぜ生活習慣病が増えたのか?
生活習慣病が増加した背景には、現代の豊かな日常生活が大きく影響しています。
- 過剰なエネルギー摂取と運動不足: 豊かな食生活は、意識せずともエネルギー過多になりがちです。その一方で、便利な生活は慢性的な運動不足を招き、消費エネルギーが減少します。この極端なエネルギーバランスの崩れが、生活習慣病を引き起こす大きな要因となっています。
- ストレスの増大: 現代社会におけるストレスの増大も、生活習慣病の発症に深く関わっています。
生活習慣病の共通点と危険性
生活習慣病の多くに共通しているのは、かなり進行するまで自覚症状がほとんど現れないという点です。そのため、健康診断でリスクを指摘されたり、異常値が出ても、本人がその重要性を認識しにくく、予防や治療への行動が遅れてしまうケースが少なくありません。
自覚症状がなくても、「健康的とは言えない生活習慣」が体への負担として確実に蓄積されていくと、やがて心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、脳出血などのより深刻な病気を引き起こす可能性があります。結果として、QOL(生活の質)が低下し、健康寿命(介助や介護を受けずに生活できる期間)が短くなるだけでなく、寿命そのものも短くなってしまうことに繋がりかねません。
主な生活習慣病の種類

生活習慣病と言われる病気には、以下のようなものが挙げられます。
- 糖尿病: 血液中の血糖値が慢性的に高くなる病気です。網膜症、腎症、神経障害といった「三大合併症」のほか、動脈硬化が進行し、脳卒中や心臓病のリスクも高くなります。
- 高血圧症: 食塩の摂りすぎ、肥満、飲酒、運動不足などが原因で、血圧が常に高い状態が続く病気です。高血圧の状態が続くと動脈硬化が進み、狭心症や心筋梗塞、心不全、脳梗塞や脳出血、認知症になりやすくなります。
- 脂質異常症(高脂血症): 血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質代謝に異常をきたした状態を指し、動脈硬化が進むことで、心筋梗塞や脳梗塞などにつながる原因となります。
- 高尿酸血症(痛風): 血液中の尿酸が多くなり過ぎてしまう病気です。尿酸塩の結晶が体のあちこちに溜まって激しい痛みを引き起こす痛風発作を起こすことがあります。プリン体の多い食品やアルコールの過剰摂取が原因となります。
- がん(悪性新生物): 喫煙、飲酒などの生活習慣や、環境物質、遺伝などがリスク要因とされています。肺がん、大腸がんなどが生活習慣病に関連するがんとして挙げられます。
- 心疾患: 心筋梗塞を含めた冠動脈疾患、不整脈、心不全などが含まれます。高血圧、糖尿病、高コレステロール、喫煙、運動不足などがリスク要因です。
- 脳血管疾患: 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の総称です。高血圧、糖尿病、高コレステロール、喫煙などがリスク要因です。
- 肝疾患(肝硬変、脂肪肝など): 過度なアルコール摂取や、生活習慣の乱れによる脂肪肝が原因で、肝機能が低下したり、肝炎から肝硬変へと進行したりする可能性があります。
- 腎疾患(慢性腎不全など): 高血圧や糖尿病などが原因で、腎臓の機能が徐々に低下する状態です。
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD): 喫煙などが原因で、気管や気管支が慢性的に炎症を起こし、咳や痰が続く状態です。
注目すべき「メタボリックシンドローム」とは?

近年、生活習慣病のリスクをより総合的に捉える概念として、「メタボリックシンドローム」が特に注目されています。
メタボリックシンドロームの診断基準
メタボリックシンドロームとは、ウエスト周囲径(へそ周りの腹囲)が男性85cm以上、女性90cm以上であることに加え、以下の3つの項目のうち2つ以上を併せ持った状態を指します。
- 高血糖: 空腹時血糖110mg/dl以上
- 高血圧: 収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
- 脂質異常: 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満
単に腹囲が大きいだけでも問題ですが、上記の項目が複数重なることで、動脈硬化の進行リスクが飛躍的に高まります。動脈硬化とは、血管が硬く厚くなったり、狭くなったりする状態で、これが進行すると、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす可能性が高まるのです。
なぜメタボが危険なのか?
メタボリックシンドロームの恐ろしい点は、自覚症状がほとんどないまま動脈硬化が進行することです。「血圧がやや高め」「血糖値が少し高め」「腹囲も少し大きい」といった個々の異常は軽度に見えても、これらが複数組み合わさることで、まるで「動脈硬化の火種が同時に複数くすぶっている状態」となり、突然深刻な病気へと発展するリスクをはらんでいます。
メタボリックシンドロームと診断された方は、そうでない方と比べて、2型糖尿病になるリスクが約3倍、心血管疾患(心臓病や脳卒中など)を生じるリスクが約1.7倍にもなると指摘されています。
あなたの体、大丈夫? メタボチェックと腹囲の目安
ご自身の体がメタボリックシンドロームのリスクを抱えていないか、以下の項目でチェックしてみましょう。
チェック1. 腹囲を測ってみよう!
健康診断で測る**「腹囲」は、へその位置で水平に測る「へそ周り」のサイズ**です。お腹を凹ませたり力を入れたりせずに、軽く息を吐いてリラックスした状態で測りましょう。
- 男性: 85cm以上で注意が必要
- 女性: 90cm以上で注意が必要
男女・年代別 腹囲のボリュームゾーン
厚生労働省のデータを見ると、腹囲のサイズは年代とともに増加する傾向にあります。
- 男性: 40代以降は半数以上が85cm以上の基準値を超えており、30代でも境界線付近に多くの人が分布しています。男性は30歳を過ぎたら特に注意が必要です。
- 女性: どの年代でも90cm以上の基準値を超える人は男性に比べて少ない傾向にありますが、やはり年齢とともに腹囲が大きくなる傾向が見られます。
チェック2. BMIを計算してみよう!
BMI(Body Mass Index:体格指数)は、身長と体重から算出される肥満度を表す国際的な指標です。
計算式:体重(kg) ÷ (身長(m) × 身長(m))= BMI
| 18.5未満 | やせ |
| 18.5以上25未満 | 普通体重 |
| 22 | 適正体重(最も病気になりにくいとされる) |
| 25以上 | 肥満(生活習慣病のリスクが高まります) |
チェック3. 健康診断の結果も確認しよう!
腹囲の数値に加え、健康診断で測定される血糖値、血圧、脂質の数値(中性脂肪、HDLコレステロール)を確認することで、ご自身のメタボリックシンドロームのリスクをより正確に把握できます。これらの数値に異常がないか、定期的にチェックすることが大切です。
生活習慣病とメタボリックシンドロームを予防する「5つの対策」
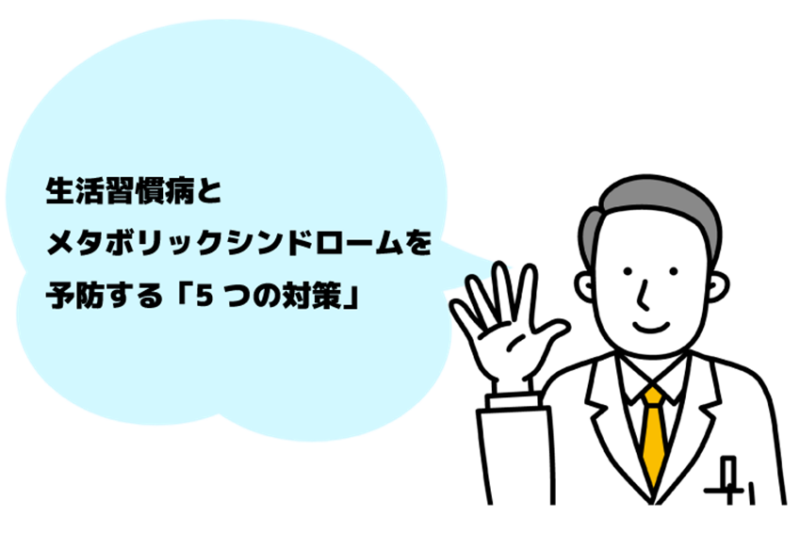
生活習慣病は、その多くが生活習慣を見直すことで予防・改善できるという特徴があります。命に関わる深刻な病気へと進行する前に、早めに対策を始めることが何よりも大切です。以下の5つの観点から、ご自身の生活習慣を見直し、改善できる点がないか考えてみましょう。
- 食事:バランスの取れた食生活を
- 腹八分目を心がける: 食べ過ぎを防ぎ、摂取エネルギーを適正に保ちましょう。
- よく噛んで食べる: 満腹感を得やすくなり、消化吸収も促進されます。
- 食物繊維を積極的に摂る: 野菜、きのこ、海藻などを多く摂ることで、血糖値の急激な上昇を抑え、コレステロールの吸収を穏やかにします。
- 塩分を控える: 高血圧予防に直結します。
- 間食や夜食は控えめに: 不要なエネルギー摂取を減らします。
- バランスの取れた献立: 主食・主菜・副菜を揃え、多様な栄養素を摂取しましょう。
- 運動:体を動かす習慣を身につける
- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、水泳など、無理なく続けられる運動を週2~5回程度取り入れましょう。内臓脂肪の減少に効果的です。
- 筋力トレーニング: スクワットやプランクなど、簡単な筋トレを週2~3回程度行うことで、基礎代謝が上がり、脂肪燃焼を促進します。特に男性は、筋肉量が多いほど内臓脂肪を燃やしやすくなります。
- 「1cm減らすのに7,000kcal」: 腹囲1cm、体重1kg減らすには、約7,000kcalのエネルギー消費が必要です。例えば、1日あたり約230kcal(おにぎり1個分程度)減らすか多く消費することを目標にしてみましょう。
- すきま時間の活用: まとまった時間が取れなくても、10分ずつの運動を複数回行うなど、無理なく継続できる方法を見つけましょう。
- 喫煙:禁煙は最大の予防策
- 喫煙は、がん、心疾患、脳血管疾患、慢性気管支炎など、あらゆる生活習慣病のリスクを大幅に高めます。禁煙は、生活習慣病予防において最も効果的な対策の一つです。
- 飲酒:適量を心がける
- 過度な飲酒は、肝疾患(脂肪肝、肝硬変)、高血圧、脂質異常症、痛風などのリスクを高めます。飲酒量や頻度を見直し、休肝日を設けるなど、適量を心がけましょう。
- 睡眠・休養:心身をリフレッシュする
- 睡眠不足やストレスは、ホルモンバランスの乱れや食欲の増進につながり、肥満や生活習慣病のリスクを高めます。
- 十分な睡眠時間を確保し、ストレス解消法を見つけるなど、心身を休ませる時間を意識的に作りましょう。趣味の時間を持つことや、友人と交流することも心の健康につながります。
健康な未来のために、今すぐできること

生活習慣病やメタボリックシンドロームは、決して他人事ではありません。まずはご自身の健康状態に関心を持ち、病気や健康に対する知識を深めることが第一歩です。そして、毎日の生活習慣をもう一度見直し、健康的な習慣を維持していきましょう。
早期に気づき、対策を始めることで、健康寿命を延ばし、充実した人生を送ることができます。今日からできることから、少しずつ始めてみませんか?
