- 2025年9月19日
夏の魚介類に潜む危険!「腸炎ビブリオ」食中毒は終わっていなかった?正しい予防法と対処法
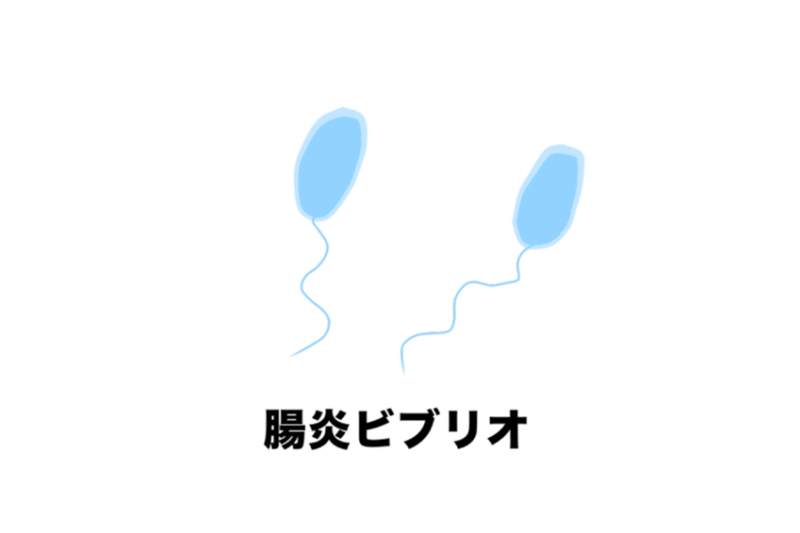
厳しい暑さが和らぎ、過ごしやすい日が増えてきましたね。明石市のたなか内科クリニックです。
さて、夏の終わりから秋にかけて、美味しい魚介類を楽しむ機会も多いのではないでしょうか。しかし、この時期に特に注意したいのが、「腸炎ビブリオ」による食中毒です。
「腸炎ビブリオって、昔流行った食中毒でしょ?」と思われている方も多いかもしれません。確かに、食品の低温管理が徹底されたことで発生件数は劇的に減少しました。しかし、先日も北海道で140名以上が発症する大規模な集団食中毒がニュースになったように、決して過去の病気ではないのです。
今回は、改めて「腸炎ビブリオ」の恐ろしさと、家庭でできる確実な予防法、そして万が一感染してしまった際の対処法まで、詳しく解説します。
そもそも「腸炎ビブリオ」とは?菌のキャラクター紹介
まず、敵の正体を知ることから始めましょう。
- すみか: 海水の中や海の泥の中。そのため魚介類に付着しやすい。
- 好きなもの: 塩分と暖かい場所。海水と同じくらいの塩分濃度(約3%)が大好きで、水温が15℃を超えると活発に増殖し始めます。
- 苦手なもの: 真水(水道水)、低温(10℃以下)、熱。
- 特技: とにかく増殖スピードが速いこと。条件が揃うと、他の食中毒菌の倍以上のスピードで増えてしまいます。
ちなみに、ノロウイルスなどとは違い、人から人へうつることはありません。
どんな症状が出るの?

感染すると、短い場合で2〜3時間、通常は8〜24時間の潜伏期間の後に、以下のような症状が現れます。
- 激しい腹痛: 突然、差し込むような強い痛みが特徴です。
- 水様性の下痢: 水のような便が何度も出ます。
- その他: 吐き気、嘔吐、38℃以下の軽い発熱、頭痛などを伴うこともあります。
症状は2〜3日で回復することが多いですが、下痢や嘔吐による脱水症状には注意が必要です。
【これが一番大事!】家庭でできる、腸炎ビブリオ食中毒・5つの鉄則

腸炎ビブリオは魚介類に付着している可能性を前提として、食中毒予防の三原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底することが何よりも重要です。
① 【つけない】調理前は「真水」でしっかり洗う!
腸炎ビブリオは真水が苦手です。魚介類の表面についた菌を洗い流すため、調理の前には水道水(流水)でしっかりと洗いましょう。
② 【ふやさない】とにかく「低温」で管理!
増殖スピードの速さが特徴の菌です。買ってきた魚介類は寄り道をせず、すぐに冷蔵庫(できれば4℃以下)で保存してください。室温での放置は絶対にやめましょう。
③ 【やっつける】加熱は「中心部」までしっかりと!
腸炎ビブリオは熱に弱く、60℃で10分以上加熱すれば死滅します。焼き魚や煮魚などは、中心部まで十分に火を通しましょう。
④⑤ 【つけない】「二次汚染」を徹底的に防ぐ!

生の魚介類を扱った手や調理器具が、他の食材を汚染することを「二次汚染」と言います。
- 生の魚介類を扱った後は、必ず石鹸で手を洗いましょう。
- 包丁やまな板は、魚介類専用のものを用意するのが理想です。難しい場合は、魚介類を切った後、すぐに洗剤でよく洗い、熱湯や塩素系漂白剤で消毒してから次の食材に使いましょう。
【特に注意が必要な方へ】重症化のリスクについて

ほとんどの場合は数日で回復しますが、以下に当てはまる方は重症化し、敗血症などを起こして命に関わる危険性があります。
- 肝臓に持病のある方(肝硬変など)
- 免疫力が低下している方(免疫抑制剤を服用中の方、HIV感染症の方など)
- 胃酸の分泌が少ない方(胃の手術後や薬を服用中の方など)
上記に当てはまる方は、予防を徹底するとともに、生の魚介類(特にカキやアサリなど)を食べるのは避けるようにしてください。また、海水浴などで皮膚に傷ができた場合、そこから菌が侵入して感染することもあるため注意が必要です。
もし感染してしまったら?家庭での対処法

激しい腹痛や下痢の症状が出た場合、まずは医療機関を受診することが基本ですが、家庭では以下の点に注意してください。
- 水分補給を最優先に: 脱水を防ぐため、お茶やスポーツドリンク、経口補水液などをこまめに飲みましょう。
- 自己判断で下痢止めを飲まない: 下痢は、体内の菌を外に出そうとする防御反応です。むやみに止めると、かえって回復を遅らせる可能性があります。
- 食事は慎重に: 下痢がひどい時は無理に食べず、水分補給に専念します。症状が少し落ち着いたら、おかゆやよく煮込んだうどんなど、消化の良いものから少量ずつ始めましょう。乳製品、冷たいもの、脂っこいもの、繊維の多いものは避けてください。
明石市にお住まい・お勤めで、魚介類を食べた後の激しい腹痛や下痢など、気になる症状がある場合は、自己判断せずにできるだけ早く当院へご相談ください。正しい知識で、安全に美味しい海の幸を楽しみましょう。
