- 2025年5月13日
お腹の張りが続くのはなぜ?原因と対策、放置すると怖い病気のサインかも

「最近、なんだかお腹が張って苦しい…」
「お腹がぽっこりしてきて、便秘かな?でも、それだけじゃない気もする…」
多くの方が一度は経験する「お腹の張り」。食べ過ぎや一時的な便秘で起こることもありますが、もしその不快な症状が長く続いたり、他の症状を伴ったりする場合は注意が必要です。「いつものこと」と自己判断せず、その原因をきちんと理解し、適切に対処することが大切です。
このブログでは、お腹の張りの原因から、ご自身でできる改善策、そしてお腹の張りの裏に隠れている可能性のある病気や医療機関受診の目安について、詳しく解説していきます。
「お腹の張り(腹部膨満感)」ってどういう状態?

腹部膨満感とは、胃や腸などの消化管が何らかの原因で膨らみ、お腹が内部から圧迫されるように感じる状態を指します。ガスが溜まっている感じ、お腹がパンパンに張る感じ、重苦しい感じなど、感じ方は人それぞれです。
なぜお腹は張るの?主な原因を探る
お腹の張りを引き起こす原因は多岐にわたります。
1. 日常生活に潜む原因
- 食べ過ぎや飲み過ぎ、早食い: 消化が追いつかず、胃腸に負担がかかります。
- 脂肪分の多い食事: 消化に時間がかかり、胃もたれやお腹の張りを引き起こしやすくなります。
- ストレスや睡眠不足: 自律神経のバランスが乱れ、胃腸の正常な働きを妨げます。
- 夜遅い時間の食事: 就寝前に食事を摂ると、消化活動が不十分になりがちです。
2. 食後にお腹が張りやすい場合
上記の原因に加え、食後に特にお腹の張りを感じやすい方は、以下のような状態が考えられます。
- 胃酸過多: 胃酸の分泌が過剰になると、胃の不快感や張りを生じることがあります。
- 逆流性食道炎: 胃酸が食道へ逆流し、胸やけだけでなく、お腹の張りを感じることもあります。
- 胃腸の動きの低下(機能性ディスペプシアなど): 胃が食べ物をうまく送り出せない、または腸の動きが悪くなっている状態です。
3. ガスが溜まってお腹が張る場合
お腹の中でガスが過剰に発生したり、うまく排出されなかったりすると、お腹が張って苦しくなります。
- 便秘: 便が腸内に長く留まると、悪玉菌が増殖し、ガスが発生しやすくなります。運動不足や加齢、食物繊維のバランスの偏り(摂りすぎ、または不足)などが便秘の原因となります。
- 腸内環境の悪化: 悪玉菌が増えると、腸内で異常な発酵が起こり、ガスが過剰に発生します。
- 食物繊維のとりすぎ: 適度な食物繊維は便通に良いですが、特定の種類の食物繊維を一度に大量に摂ると、腸内でガスを発生させやすくなることがあります。
まずは試してみよう!自分でできるお腹の張りの改善策
つらいお腹の張りを和らげるために、日常生活でできることから始めてみましょう。
【食事編】
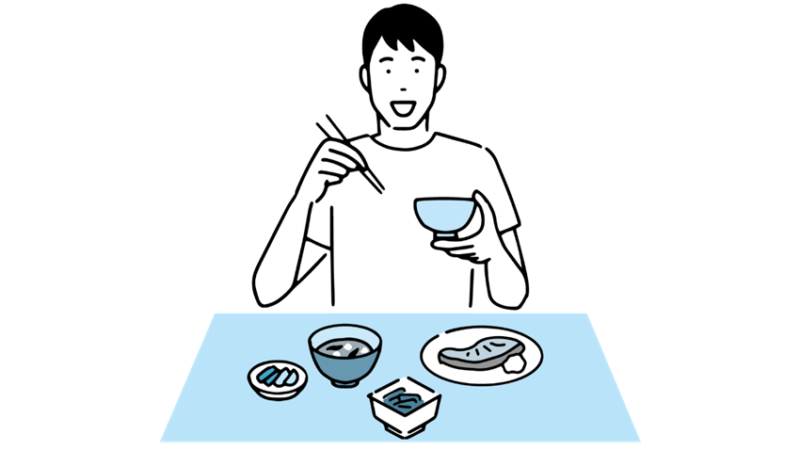
- 暴飲暴食を避ける: 「腹八分目」を心がけ、胃腸に負担をかけないようにしましょう。
- ゆっくり、よく噛んで食べる: 早食いは禁物です。よく噛むことで消化を助け、空気の飲み込みも減らせます。
- 脂肪分の多い食事は控えめに: 消化の良いものを選びましょう。
- ガスを発生させやすい食品に注意: 豆類、いも類、玉ねぎ、キャベツ、根菜類などは、摂りすぎるとお腹でガスを発生させやすいことがあります。白米やパン、麺類などの炭水化物も、人によってはガスの原因になることがあるため、食べ過ぎに注意しましょう。
- バランスの取れた食生活: 特定の食品に偏らず、多様な食品をバランス良く摂ることが大切です。
【生活習慣編】

- 適度な運動: ウォーキングなどの有酸素運動は、腸の動きを活発にし、便秘解消やストレス軽減にも役立ちます。
- 十分な睡眠: 質の良い睡眠は自律神経を整え、胃腸の働きを正常に保ちます。
- ストレスを上手に解消する: 自分に合ったリフレッシュ方法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
- 便秘にならない工夫を: 定期的な排便習慣を意識し、必要であれば医師に相談しましょう。
そのお腹の張り、もしかしたら病気のサインかも?
生活習慣を見直してもお腹の張りが改善しない、または以下のような症状がある場合は、何らかの病気が隠れている可能性があります。自己判断せずに、必ず医療機関を受診しましょう。
胃炎(急性胃炎・慢性胃炎)
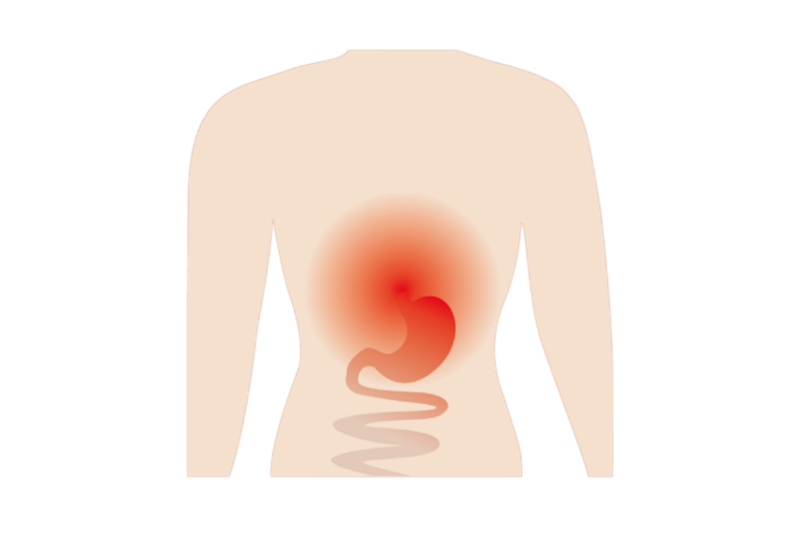
急性胃炎
アルコールや刺激物の摂取、ストレス、ウイルス感染などが原因で、突然みぞおちがキリキリ痛むことがあります。胃粘膜がただれたり(びらん性胃炎)、充血したりします。
慢性胃炎
長期間にわたり胃の粘膜に炎症が続く状態で、多くはピロリ菌感染が原因とされています。慢性胃炎が進行すると、胃粘膜が薄く痩せてしまう「萎縮性胃炎」となり、胃がんの発生リスクが高まることが知られています。胃がん予防のためにも、ピロリ菌の検査と適切な治療(除菌など)が重要です。
過敏性腸症候群(IBS)
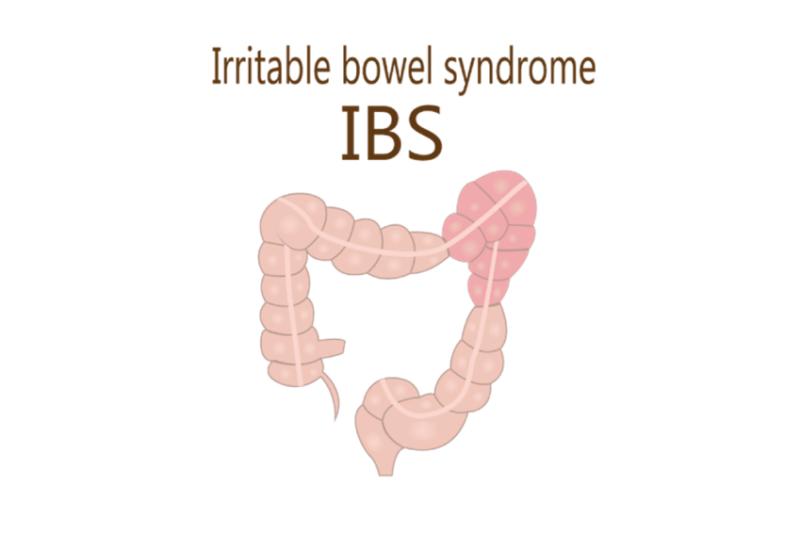
ストレスなどが引き金となり、腸のぜん動運動(内容物を運ぶ動き)に異常が生じ、腹痛を伴う下痢や便秘を繰り返す病気です。お腹の膨満感を強く感じる方も多く、下痢型、便秘型、混合型(下痢と便秘を繰り返す)などのタイプがあります。それぞれのタイプに合った治療法があります。
がん(消化器系のがん、婦人科系のがんなど)

大腸がん、胃がん、膵臓がん、卵巣腫瘍(女性の場合)などのがんが進行すると、お腹の張り(腹部膨満感)を引き起こすことがあります。これらの病気は、初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、お腹の張りや食欲不振などをきっかけに検査を受けて発見されることも少なくありません。
お腹の張りが続く、食欲がない…そんな時は迷わず医療機関へ

「お腹の張りがもう何週間も続いている」
「食欲がなくて、体重も減ってきた」
「お腹の張りに加えて、腹痛や吐き気もある」
このような場合は、放置せずに速やかに消化器内科などの専門医を受診しましょう。インターネットで症状を検索して不安を募らせるよりも、専門医による正確な診断と適切なアドバイスを受けることが、問題解決への一番の近道です。
医療機関では、まず詳しい問診(症状、食生活、生活習慣、既往歴など)と腹部の診察を行います。その上で、医師が必要と判断した場合に、以下のような検査を組み合わせて総合的に診断し、適切な治療法を検討します。
- 胃カメラ(上部消化管内視鏡検査): 食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察し、炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどの有無を確認します。
- 大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査): 大腸全体の粘膜を観察し、ポリープ、がん、炎症性疾患などがないか調べます。
- 腹部超音波(エコー)検査: 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓といった腹部の臓器や、場合によっては腸の状態、腹水の有無などを確認します。
- その他:血液検査や便検査、CT検査などが行われることもあります。
逆流性食道炎や機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群などは、適切な薬物療法や生活習慣の改善で症状が良くなることが期待できます。
お腹の張りは、日常的な原因から深刻な病気まで、様々な要因によって引き起こされます。まずはご自身の生活習慣を見直し、改善できる点に取り組んでみましょう。それでも症状が続く場合や、気になる症状がある場合は、決して自己判断せずに、早めに消化器内科を受診することが大切です。
当院では、お腹の張りの原因を特定するための各種検査に対応しており、経験豊富な専門医が丁寧な診療を心がけております。お気軽にご相談ください。つらいお腹の症状から解放され、快適な毎日を送るために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
※腹部膨満感(お腹の張り)について 比較的多い症状の一つとなります。
原因はさまざまですが、やはり腸の動きが影響している場合が多いです。「毎日排便がある」といった場合でも実際は運動不足等での便秘傾向が原因であったりもします。
しかしある程度の年齢の方の場合は、何らかの初期症状の場合もあるため、一度は大腸の検査をお勧めしています。大腸の検査にて異常が無いことを確認していれば、お薬での調整を継続して行っていきます。
