- 2025年11月14日
健康診断で「要精密検査・要経過観察」と通知されたら?健診結果を健康管理に活かす!
その健康診断結果、まだ「放置」していませんか?
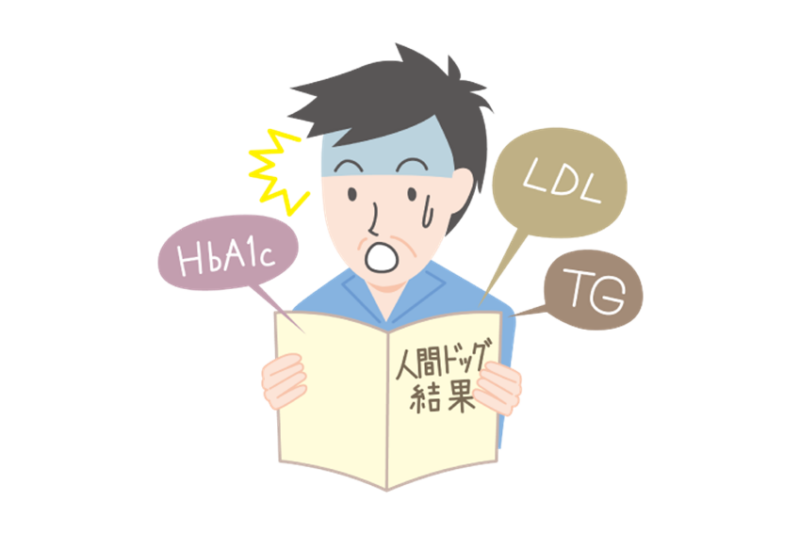
毎年受けている健康診断。結果が届いたとき、「異常なし」だと安心しますよね。でも、もし「要精密検査」や「要経過観察」という通知が来たら、不安を感じつつも、ついつい放置してしまっていませんか?
「面倒だから後回しに…」「忙しくて時間がない」「病気が見つかるのが怖い…」「自分で生活習慣を変えれば大丈夫だろう」。そう考えて、通知を放置してしまっている方も少なくないかもしれません。
しかし、それではせっかく健康診断を受けた意味がありません。これらの通知は、あなたの健康を守るための大切なサイン”です。健康診断の結果をしっかり受け止め、適切な対応を行うことが、その後の健康や生活の質向上に繋がります。
この記事では、健康診断で異常を指摘された方が、次に何をすべきか、具体的な症状別の対処法、そして当院での対応について、消化器内科の医師の視点から詳しく解説します。あなたの不安を解消し、適切な医療へとスムーズに繋げるために、ぜひ最後までお読みください。
1. 健康診断の結果、どう判断したらいい?判定区分の意味
健康診断の結果報告書には、各検査項目ごとに判定区分が記されています。それぞれの意味を理解し、的確な対応を行いましょう。
| 異常なし | 項目の測定数値が正常範囲内で、機能的に問題ないという事が示されています。 |
| 要経過観察・要再検査 | 測定数値は正常範囲を超えているものの、すぐに治療を必要とする状態ではありません。この診断結果を受けて、生活習慣や食事の改善を図り、病気の予防や健康維持を心がけましょう。 当院では、診断結果を踏まえた生活習慣改善についてのアドバイスもおこなっていますので、お気軽にご相談下さい。 |
| 要精密検査 | 健康診断の検査だけでは特定が難しい病気が疑われる場合に、さらに詳しく調べてみる必要があるという意味の診断結果です。必ず病気があるという深刻な状態というわけではなく、異常が見つからないケースもあります。必要以上に検査結果を深刻に受け止める必要はありません。「要精密検査」が出た場合は、なるべく早めに精密検査を受けましょう。 当院では、精密検査や2次検査にも対応していますので、ご相談下さい。 |
| 要治療 | すぐに治療が必要な異常値が見つかったという状態です。なるべく早めに専門の医療機関を受診し、的確な診断と最適な治療についてしっかり相談してください。 これらの結果を正確に理解し、健康管理に活かしていくことが大切です。 |
2. 異常を指摘されたらどうする?各検査項目でわかることと対処法

健康診断では検査項目ごとに病気のリスクを判定しています。数値が正常範囲を超えた場合、どのような病気が考えられるのか、そしてどう対処すべきかを見ていきましょう。
2-1. 血圧:「自宅では正常なのに…」
血圧測定で最高血圧(収縮期)と最低血圧(拡張期)のどちらかが正常範囲を超える場合、高血圧と判定されます。高血圧は血管に負担がかかり続け、動脈硬化や脳出血、脳梗塞などの発症リスクを高めます。
病院で血圧を測ると緊張で数値が高くなる「白衣高血圧」という現象もあります。ご自宅でリラックスして測った血圧が正常値だった場合は、その結果も持参して受診することをおすすめします。
2-2. メタボリックシンドローム:「基準該当」や「予備軍」と言われたら?
血糖、血圧、脂質の数値と腹囲から総合的に診断されます。「基準該当」や「予備軍該当」とされた場合、体内に内臓脂肪が多く蓄積されており、動脈硬化を引き起こす恐れがあります。さらに進行すると、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などのリスクが高まるため、治療や生活習慣の改善に早期に取り組むことが病気の予防に繋がります。
2-3. コレステロール:「善玉と悪玉、どっちが悪いの?」
血液中の善玉コレステロール(HDL)と悪玉コレステロール(LDL)の量を測り、動脈硬化のリスクを判定します。
| 善玉コレステロール(HDL) | 動脈硬化を防ぐ働きがあるため、量が少ないとリスクが高まります。 |
| 悪玉コレステロール(LDL) | 動脈硬化を進行させる働きがあるため、量が多いと注意が必要です。 |
善玉・悪玉コレステロールのバランスを見て、生活習慣の改善を行うことで病気リスクを抑えることができます。自覚症状がない場合が多いため、指摘されたら早めに対処しましょう。
2-4. 血糖値:「糖尿病の予兆?」
血液中のブドウ糖の量を測り、糖尿病のリスクを調べます。糖尿病は常に血糖値が高い状態が続き血管に負担をかけ続けるため、動脈硬化や脳出血、脳梗塞、心筋梗塞を発症するリスクが高くなります。さらに、失明、足指の壊死、腎機能障害(透析治療が必要になることも)といった重大な合併症を引き起こす恐れもあります。
糖尿病の初期は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行するので、健康診断で異常を指摘されたらすぐに医師の診察を受けましょう。
2-5. 尿酸値:「ビールを控えたら大丈夫?」
尿酸値が高いと、血管や腎臓に負担をかけ、激しい痛みを伴う痛風を引き起こす恐れがあります。ビールなど、プリン体を多く含む食品や飲料を過剰に摂取すると尿酸値が上昇しやすいです。
尿酸値が基準を超える場合、飲み物や食べ物の制限と合わせて適度な運動を行い、十分な水分補給を心がけることが大切です。ビールだけでなく、アルコール自体を控えるようにしましょう。
2-6. 肝機能:「沈黙の臓器」肝臓からのサイン
体内の酵素、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの数値を調べることで、肝疾患の有無やアルコール・薬の影響による肝障害を判定します。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気が進行するまで自覚症状が出にくいのが特徴です。そのため、健康診断で肝機能の数値が正常値を超えた場合は、なるべく早めに医療機関を受診して精密検査を受けましょう。肝臓への血流が滞ると、胃や食道に静脈瘤ができ、破裂すると命に関わる危険があるため、異常が見られたら早期に専門医を受診してください。
2-7. 貧血:「内視鏡検査が必要?」
血液中の赤血球の数や血色素量などを調べることで、貧血の有無を判定します。貧血の原因は鉄分不足の他に、消化器のどこかで出血が起こっている可能性もあります。
特に40歳以上の方で貧血を指摘された場合、胃潰瘍・胃がんや大腸がんなどによる慢性的な出血が原因の可能性も考えられるため、必要に応じて内視鏡検査で消化器に出血がないかを調べ、速やかに受診してください。
2-8. 尿検査:「異常あり、でも痛くない」
尿検査では、尿中に含まれるブドウ糖、たん白、赤血球などを調べます。正常値を超える場合、尿路感染症、尿路結石、腎機能障害、腎炎、糖尿病、腫瘍などの病気が疑われます。強い痛みなどの症状がある場合は、すぐに精密検査を受けましょう。
尿は食事内容に左右されやすいため、健康診断で異常所見が見られても、精密検査では異常なしというケースも多くあります。しかし、自己判断はせず、医師の指示に従いましょう。
2-9. 心電図:「心臓に異常?」
心電図検査は、不整脈や狭心症、心筋梗塞、心肥大などの心臓病の兆候がないかを調べます。心電図で「要観察」や「要精密検査」の結果が出た場合は、早めに医療機関を受診しましょう。特に、息切れや胸の痛みなどの症状がある場合は、すぐに専門医に相談してください。
おわりに:健診結果を活かして、明石市「たなか内科クリニック」へご相談ください

健康診断の結果は、あなたの現在の健康状態を知り、将来の病気を予防するための大切な「羅針盤」です。特に「要精密検査」や「要経過観察」といった通知は、決して放置してはいけません。早期発見・早期治療、または生活習慣の改善によって、より健康で質の高い生活を送るためのチャンスです。
「どこに相談したらいいか分からない」「このくらいの症状で病院に行っていいのかな?」と迷ったら、明石市のJR大久保駅北口すぐにある「たなか内科クリニック」にご相談ください。駅チカでアクセス抜群のため、明石市内はもちろん、神戸市西区、加古川市、高砂市など周辺地域からも多くの患者様にご来院いただいております。
私たちは、健診結果を踏まえた生活習慣改善のアドバイスはもちろん、丁寧な問診と診察、必要に応じた精密検査(胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査、腹部エコーなど)を行います。万が一、当院で対応が難しい場合やさらに専門的な治療が必要な場合は、責任をもって専門病院へご紹介させていただきますので、ご安心ください。
あなたの健康と安心のために、たなか内科クリニックが全力でサポートいたします。健診結果でご不安な点がある方は、JR大久保駅北口すぐのたなか内科クリニックへお気軽にご来院ください。
