- 2025年5月13日
- 2025年8月29日
魚の骨が喉に刺さったかも?食道や胃まで行くと危険?正しい対処法と病院での処置

「あれ?なんだか喉がチクチクする…もしかして魚の骨が刺さったかも?」
美味しい魚料理を楽しんだ後、そんな経験をされた方はいらっしゃるのではないでしょうか。喉の違和感は気になりますし、「このまま放っておいて大丈夫かな?」「もし変なところに刺さっていたらどうしよう…」と不安になりますよね。
魚の骨が喉に刺さることは、決して珍しいことではありません。多くは自然に取れたり、簡単な処置で済んだりしますが、場合によっては注意が必要なケースもあります。特に、骨が食道や胃まで進んでしまうと、思わぬトラブルを引き起こす可能性もゼロではありません。
この記事では、魚の骨が喉に刺さったかもしれないと感じた時の正しい対処法、やってはいけないNG行動、そして安心して医療機関を受診するための目安や病院での処置について、専門医の視点から分かりやすく解説します。この記事を読んで、万が一の時に落ち着いて対応できるようになりましょう。
本当に刺さってる?喉の症状と刺さりやすい場所
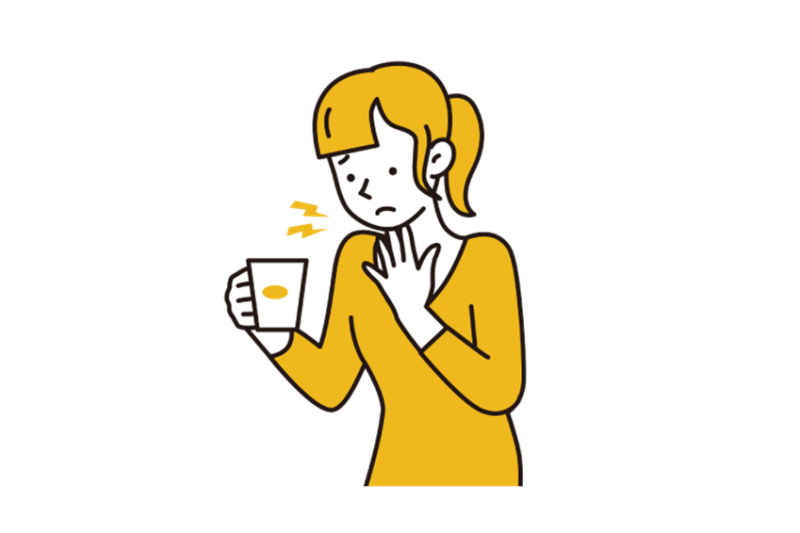
魚の骨が喉に刺さると、以下のような症状が出ることが一般的です。
- 喉の特定の部分にチクチク、ズキズキとした痛みがある
- 唾を飲み込むと痛みが強くなる
- 異物感、何かが引っかかっている感じがする
- 咳が出る、声がかすれる(まれに)
魚の骨は、主に扁桃(へんとう)や舌根(ぜっこん:舌の付け根あたり)といった場所に刺さりやすいと言われています。口を大きく開けて鏡で見てみると、運が良ければ刺さっている骨が見えることもありますが、奥の方や見えにくい場所に刺さっていることも少なくありません。
喉だけじゃない!魚の骨が食道や胃まで達するリスクとは?
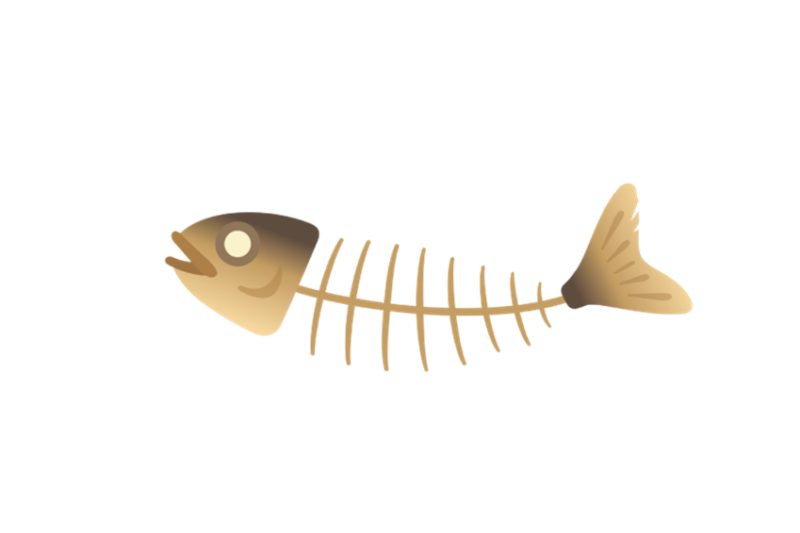
「小さな骨だし、そのうち取れるだろう」「飲み込んじゃえば大丈夫」と軽く考えてしまうのは少し危険かもしれません。確かに、細くて小さな骨であれば、食事や唾液と一緒に自然に胃へ流れ込み、消化されたり便として排出されたりすることがほとんどです。
しかし、ある程度の大きさや太さのある骨、あるいは鋭く尖った骨が喉の奥や食道に深く刺さってしまったり、気づかないうちに食道や胃まで到達して粘膜に傷をつけたりすると、以下のような問題を引き起こす可能性があります。
- 食道炎・胃炎・腸炎: 骨が粘膜を傷つけ、炎症を起こします。痛みや不快感が続く原因となります。
- 潰瘍・出血: 傷が深くなると潰瘍ができたり、出血したりすることがあります。
- 穿孔(せんこう): 非常に稀ですが、食道や胃、腸の壁に穴が開いてしまう最も危険な状態です。内容物が漏れ出し、**縦隔炎(じゅうかくえん)や腹膜炎(ふくまくえん)**といった命に関わる重篤な感染症を引き起こすことがあります。
- 膿瘍(のうよう)形成: 傷ついた部分で細菌が繁殖し、膿のたまりができてしまうことがあります。
特に、食道は心臓や太い血管、肺といった重要な臓器に近接しているため、食道に刺さった骨が原因で周囲に炎症が広がると、深刻な事態を招くことがあります。
「たかが魚の骨」と侮らず、症状が続く場合は専門医に相談することが大切です。
魚の骨が刺さったかも…まず何をすべき?自分でできる正しい応急処置

喉に魚の骨が刺さったかもしれないと感じたら、まずは慌てずに以下のことを試してみてください。
- うがいをする: 口の中に水を含み、優しくうがいをしてみましょう。浅いところに刺さっている小さな骨であれば、水流で取れることがあります。何度か繰り返してみてください。
- 唾を飲み込んでみる: 意識して何度か唾を飲み込んでみましょう。こちらも小さな骨であれば、唾液と一緒に自然に食道へ流れてくれることがあります。
これらの方法で違和感がなくなれば、ひとまず安心です。ただし、痛みが残る場合は無理をしないでください。
これはNG!悪化させる可能性のある間違った対処法

昔から「魚の骨が刺さったらご飯を丸呑みすると良い」といった話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは絶対に行ってはいけない代表的なNG対処法です。他にも、良かれと思ってやったことが状況を悪化させてしまうことがあります。
ご飯やパンなどを丸飲みする
最もよく聞く対処法ですが、非常に危険です。刺さっている骨をさらに深く押し込んでしまったり、骨の頭が見えなくなって病院での処置を困難にしてしまったりすることがあります。最悪の場合、食道の粘膜を大きく傷つけたり、穿孔のリスクを高めたりします。
指やピンセットで無理に取ろうとする
見える場所に骨があっても、自分で取ろうとするのは避けましょう。指で触ることでかえって骨を奥に押し込んだり、粘膜を傷つけて出血させたり、感染を引き起こしたりする可能性があります。ピンセットなどの器具を使うのはさらに危険です。
そのまま放置する(症状が続く場合)
「そのうち治るだろう」と痛みを我慢して放置し続けると、前述のような炎症や感染のリスクが高まります。
酢を飲む
「酢で骨が溶ける・柔らかくなる」という説もありますが、医学的な根拠は乏しく、効果は期待できません。むしろ喉を刺激してしまう可能性があります。
これらの間違った対処法は、症状を悪化させるだけでなく、診断や治療を遅らせることにも繋がります。
こんな症状は要注意!すぐに病院を受診すべきケースと診療科

自分でできる対処法を試しても改善しない場合や、以下のような症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
- 痛みが強い、または我慢できないほどの痛みがある
- 唾を飲み込むのも辛い、飲食ができない
- 声がかすれる、呼吸が苦しい感じがする
- 口から血が出ている、または血の味がする
- 異物感がまったく取れない、むしろ強くなっている
- 一晩経っても症状が改善しない、または悪化している
- 発熱が見られる(感染のサインかもしれません)
これらの症状がある場合は、自己判断せずに専門医の診察を受けることが重要です。
病院ではどんな検査や処置をするの?

医療機関では、まず患者さんから詳しい状況(いつ、何を食べて、どのような症状があるかなど)を伺います。その後、以下のような検査や処置が行われるのが一般的です。
- 視診・触診: 口の中や喉の奥をライトで照らして観察します。
- 喉頭鏡(こうとうきょう)・鼻咽腔ファイバースコープ検査: 口から、あるいは鼻から細いカメラ(内視鏡)を挿入し、喉の奥や食道の入り口付近を詳しく観察します。この検査で骨が見つかれば、多くの場合、専用の鉗子(かんし:ものをつかむ器具)を使ってその場で取り除くことができます。局所麻酔を使用することもあります。
- レントゲン検査・CT検査: 大きな骨や、食道の深い部分に刺さっている可能性がある場合、骨の位置や大きさを確認するために行われることがあります。ただし、魚の骨は写りにくいこともあります。
- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ): 骨が食道や胃にまで達している疑いがある場合や、他の検査で見つからないものの症状が強い場合に行われます。胃カメラを使って食道や胃の内部を直接観察し、骨があれば回収します。必要に応じて、傷の状態を確認したり、止血処置を行ったりすることもあります。
当院のような内視鏡クリニックでは、特にファイバースコープや上部消化管内視鏡を用いた精密な検査と安全な異物除去を得意としています。処置は通常、数分程度で終わることが多いですが、骨の刺さり方や場所によっては、より慎重な対応が必要となることもあります。
日頃からできる予防策:美味しく魚を食べるために

魚の骨によるトラブルを完全に防ぐのは難しいかもしれませんが、以下の点に気をつけることでリスクを減らすことができます。
- よく噛んで食べる: 食事の基本ですが、しっかり噛むことで骨に気づきやすくなります。
- 骨の多い魚や小骨の多い魚を食べる時は特に注意する: アジ、イワシ、サンマ、ウナギ、ハモなどは骨が多い魚の代表です。食べる際はより慎重に。
- 調理法を工夫する: 圧力鍋で調理すると骨まで柔らかくなることがあります。また、三枚おろしにするなど、調理の段階でできるだけ骨を取り除くのも有効です。
- 子どもや高齢者には特に配慮する: 食べる前に骨を丁寧に取り除いてあげたり、骨が少ない魚を選んだりするなどの配慮が大切です。
魚の骨、小さな油断が大きなトラブルに。不安な時は迷わず専門医にご相談ください
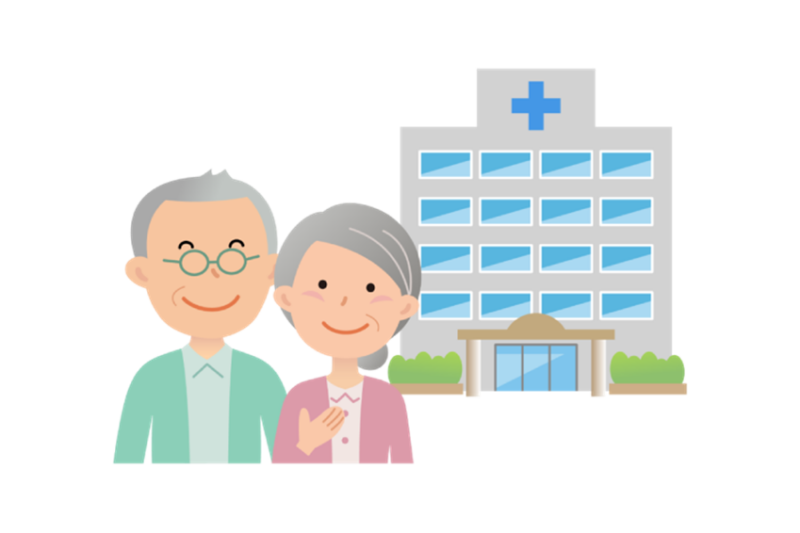
魚の骨が喉に刺さるというアクシデントは誰にでも起こり得ます。多くは軽症で済みますが、間違った対処をしたり、放置したりすることで、思わぬトラブルに発展することもあります。
喉の違和感や痛みが続く場合は、「そのうち治るだろう」と自己判断せずに、早めに専門医の診察を受けましょう。
当院では、喉の異物感から、食道・胃の異物に関するご相談まで、専門的な知識と経験豊富な医師が丁寧に対応いたします。内視鏡を用いた精密な検査と安全な処置を心がけておりますので、魚の骨が刺さったかもしれないとご不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。
※魚の骨が刺さった、もしくは刺さった感じがする、といった事が皆さん一度はあると思います。一時的に炎症を起こした場所が、喉の不快感として残ることがありますが、その場合は1日程度で良くなります。時に違和感が続く場合は骨が刺さったままの場合があります。骨は大きければCTにて確認できますが小さい場合は内視鏡にて確認する必要があります。骨が残っている場合は、透明なキャップを内視鏡の先端に取り付け、骨の回収時に周囲に傷が付きにくい工夫をして除去を行います。
当院ではその場合でも可能な限り鎮静剤を使用し、患者さんへの負担を減らしての検査を考えております。違和感が続く場合は一度ご相談ください。 なお、首が腫れてきている場合や発熱を伴う場合は迷わずに病院への受診をお勧めします。骨が刺さった部分で感染を起こしている疑いがあります。
